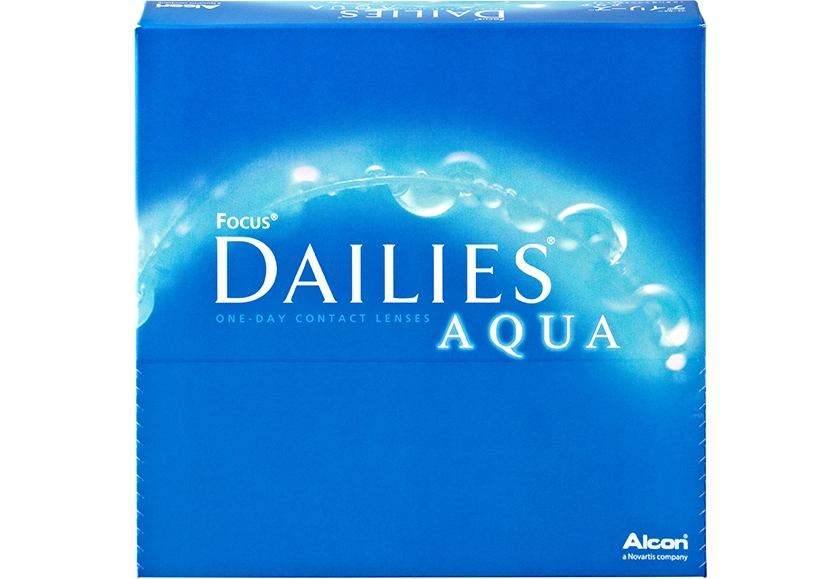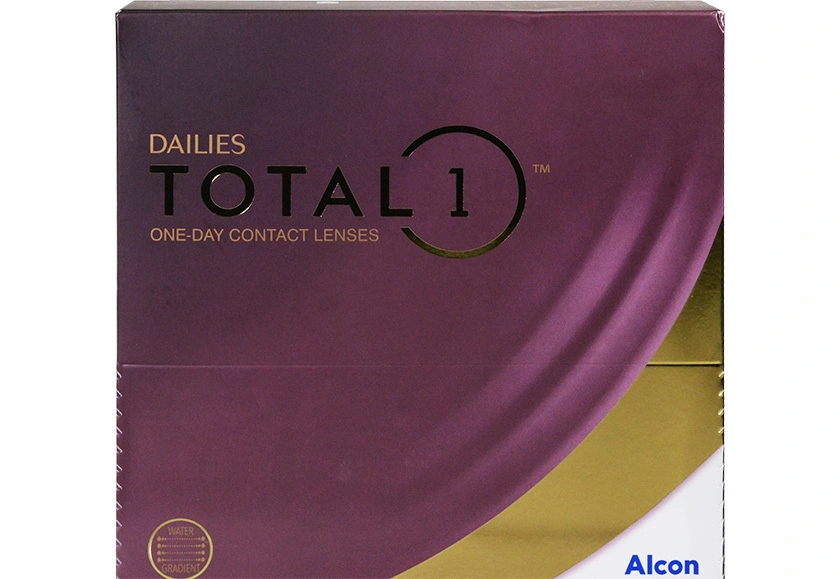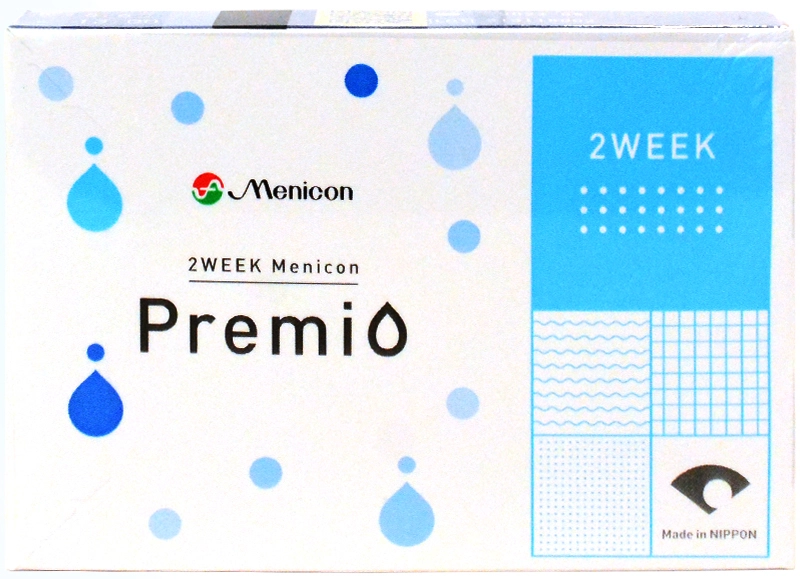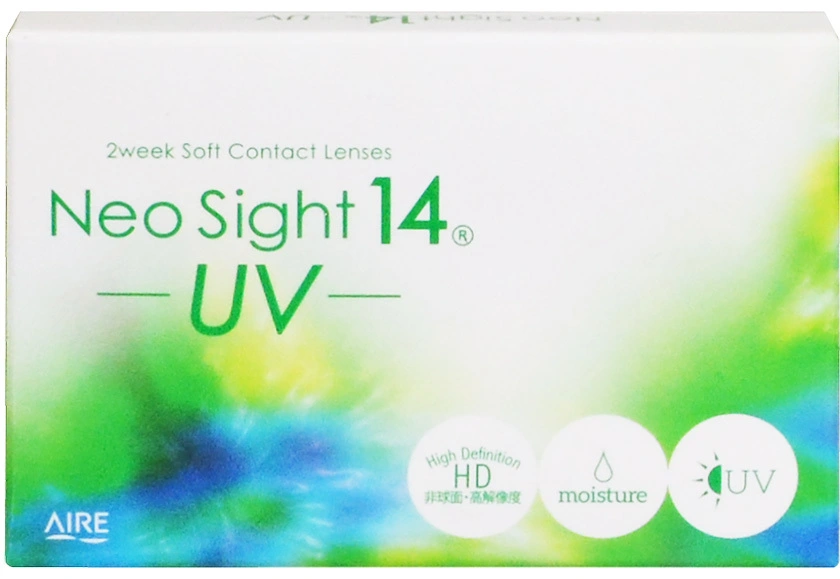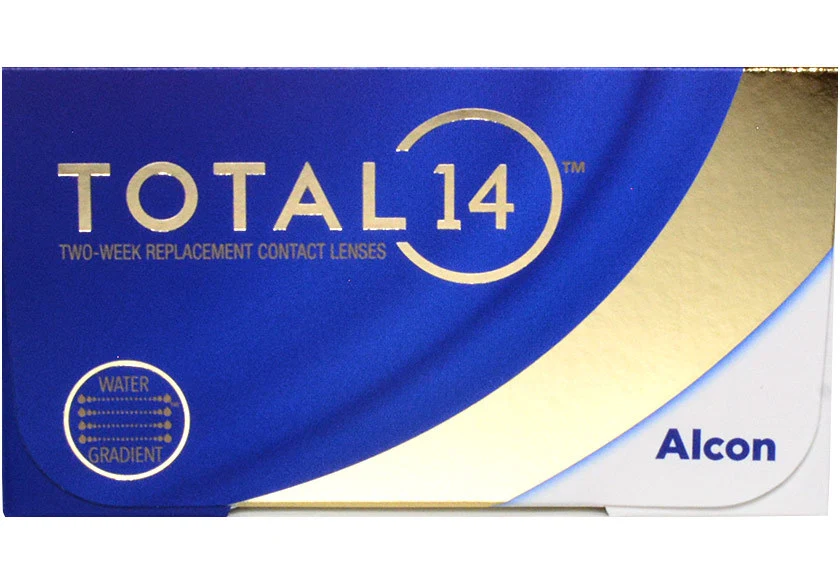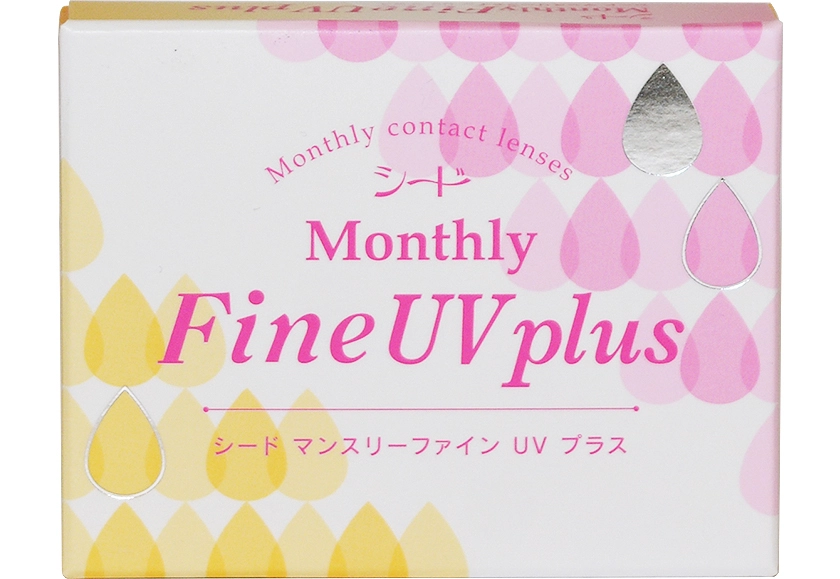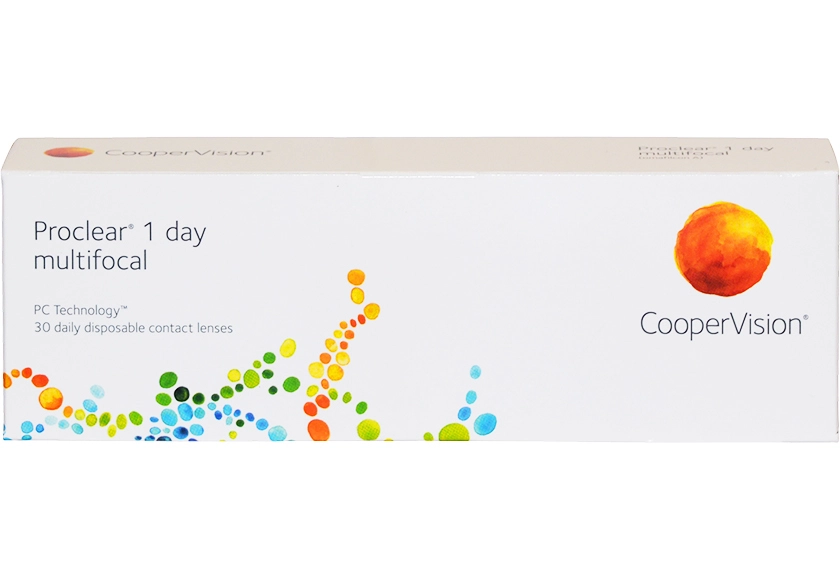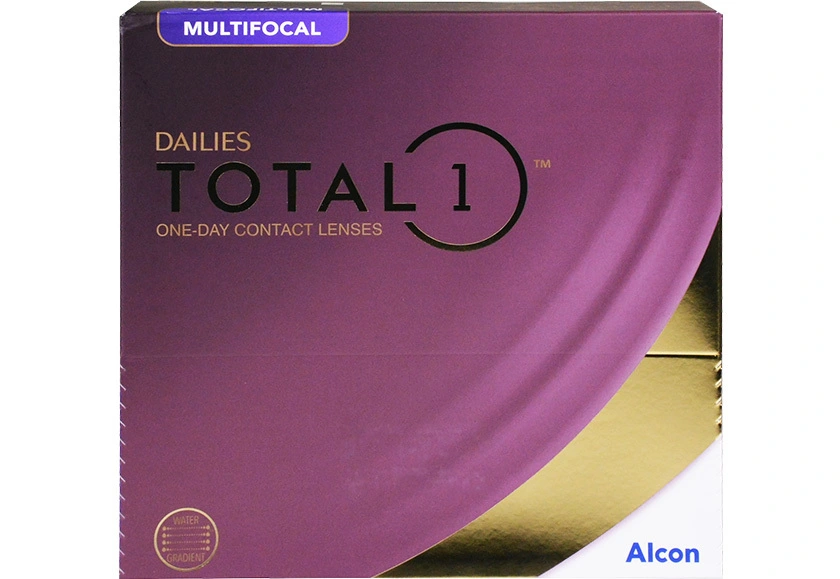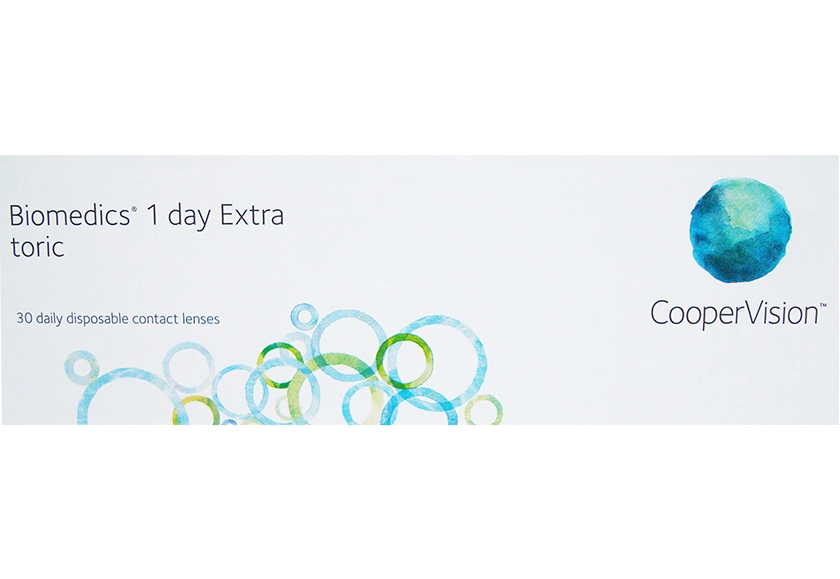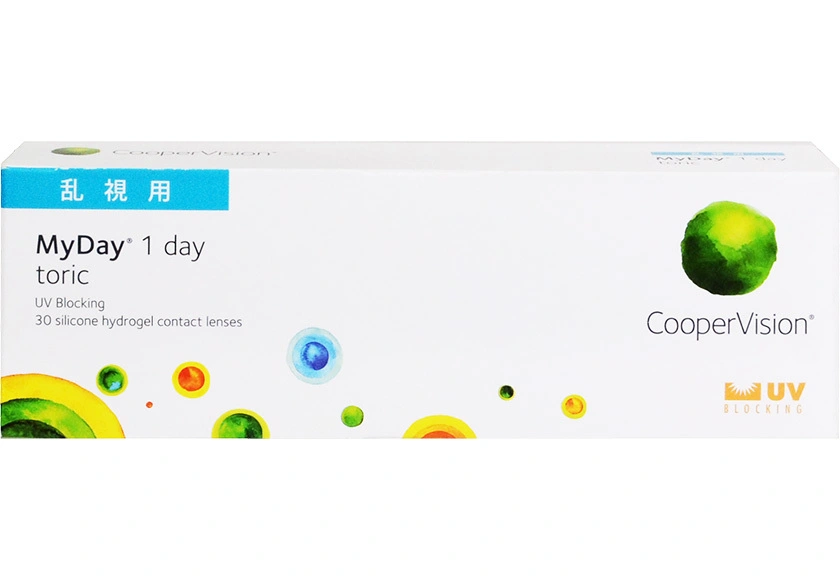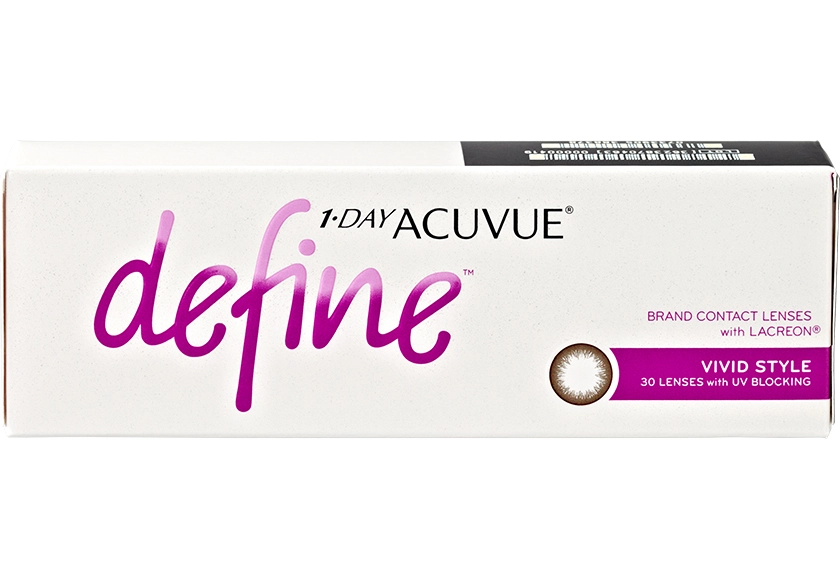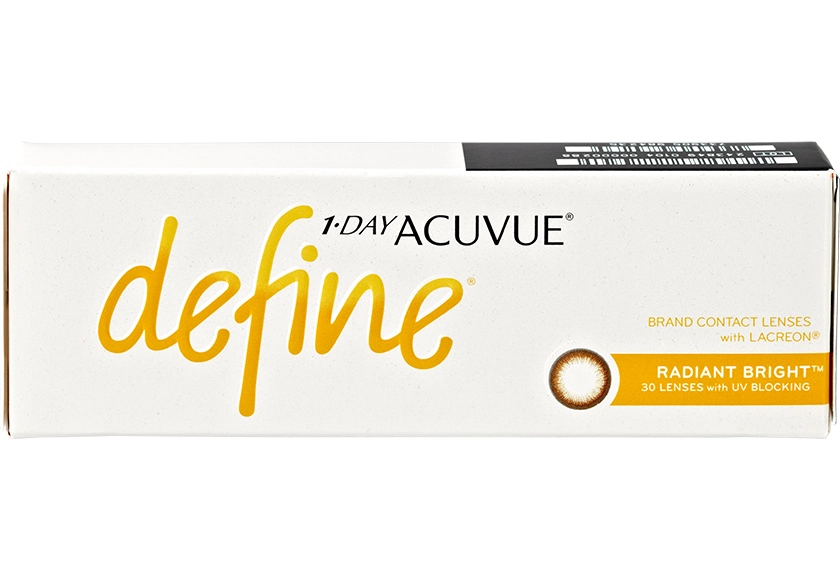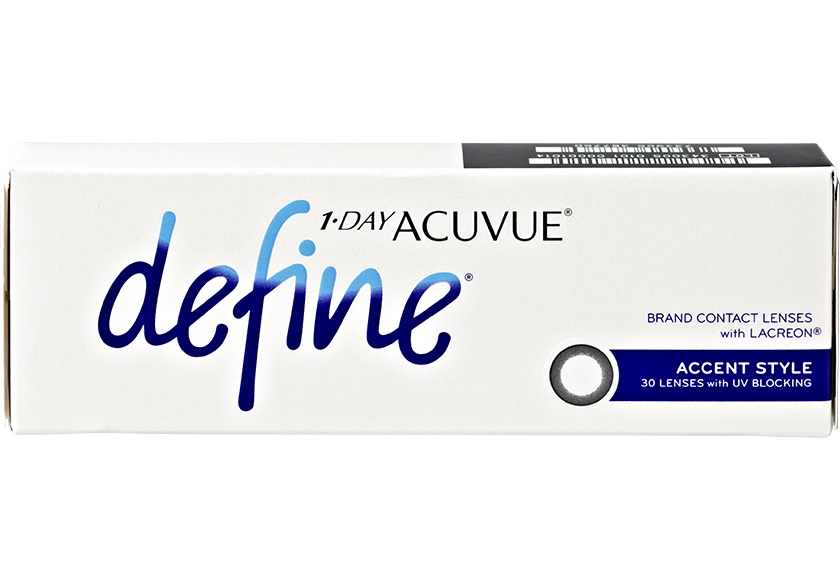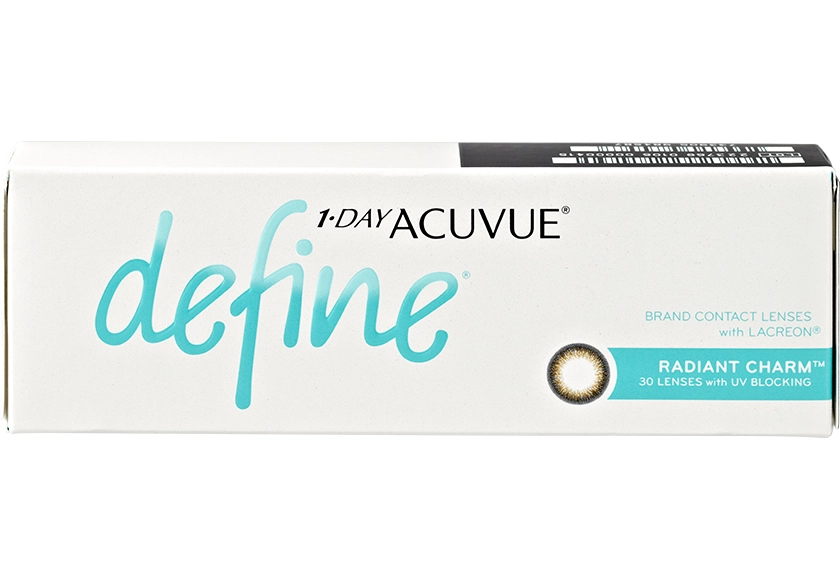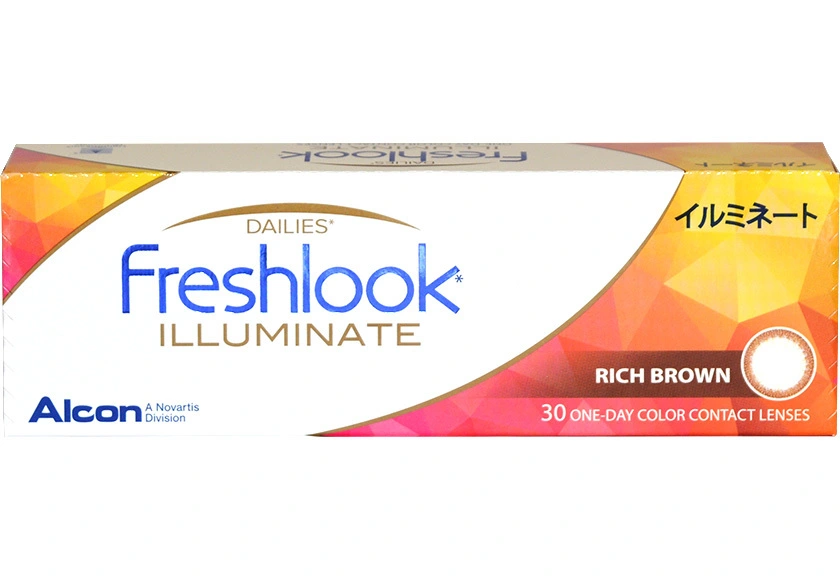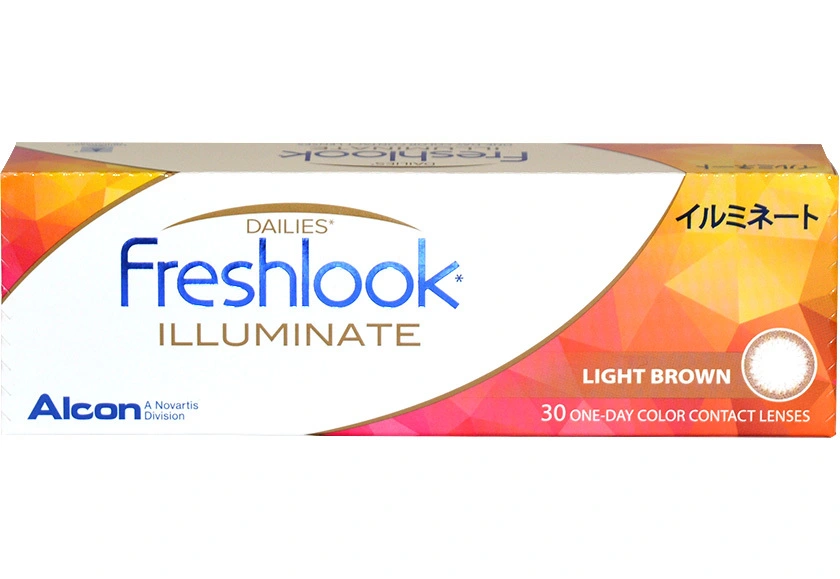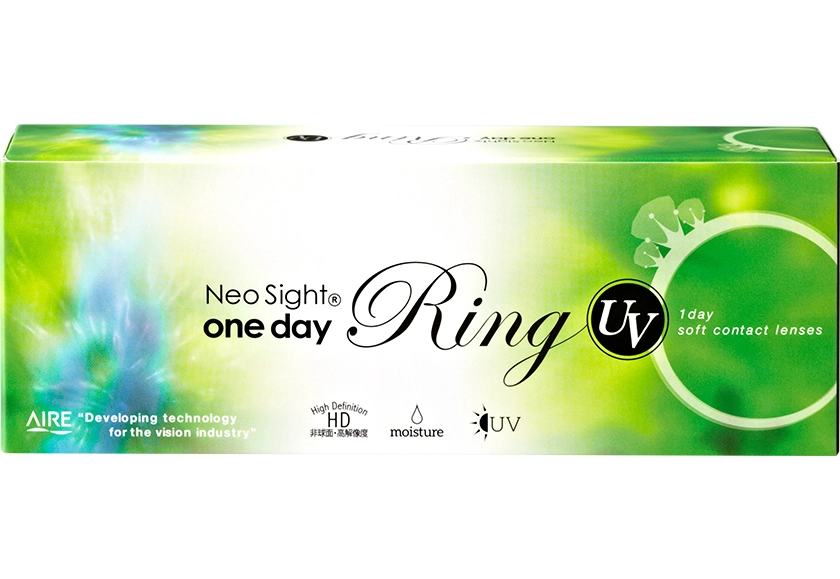生感覚のコンタクトレンズ「アルコンデイリーズトータルワン」を徹底解説!
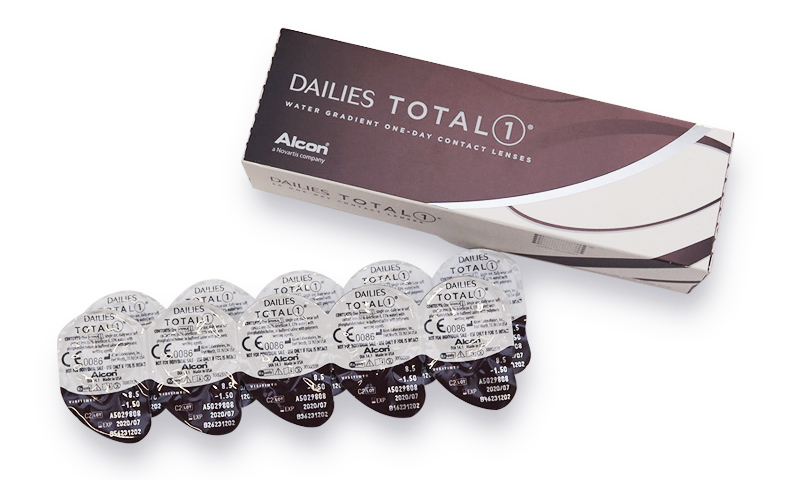
「まるで何もつけていないかのような生感覚」——これは、アルコン社のワンデーコンタクトレンズ「デイリーズトータルワン」を表すキャッチフレーズです。
本記事では、この「生感覚」の秘密を徹底解説します。独自の「水のグラデーション構造」やトップクラスの酸素透過率が、なぜ目の乾燥や違和感を軽減し、快適なつけ心地を長時間持続させるのかを詳しくご紹介。長時間のPC・スマホ作業で目の乾きに悩む方や、より目の健康を重視したい方に、本製品がおすすめできる理由と、購入前に知っておくべき注意点まで網羅します。この記事を読めば、あなたが求める理想のコンタクトレンズかどうかを判断できるでしょう。
目次
「デイリーズトータルワン」の特徴は?

「デイリーズトータルワン」は、アルコン社が販売するワンデータイプの使い捨てコンタクトレンズです。特に装用感と機能性の高さから、「生感覚レンズ」とも称されており、数あるコンタクトレンズの中でも質の高いつけ心地が期待できる商品です。
このセクションでは、「デイリーズトータルワン」がなぜそのように評価されているのか、具体的な3つの主要な特徴とラインナップを解説します。
「水のグラデーション構造」による生感覚
デイリーズトータルワン最大の特徴は、独自の「水のグラデーション構造」です。この技術により、まるで何もつけていないかのような「生感覚」の装用感が長時間持続するとされています。
一般的な含水率の違いと課題
- 含水率が高いレンズは、みずみずしいつけ心地がある一方で、水分の蒸発により乾燥しやすいというデメリットがあります。また、柔らかすぎるため扱いにくいと感じる方もいるそうです。
- 含水率が低いレンズは、水分の蒸発が抑えられやすい反面、つけ心地で違和感が生じることがあり、特にコンタクトレンズ初心者には不向きな場合があります。
水のグラデーション構造のメリット:
- トータルワンは、レンズのコア(中心部)の含水率を低く、表面(目の接触部)の含水率を高く設計しています。
- コア部分の含水率が低いため、水分の蒸発が抑えられやすく、うるおいをキープするサポートが期待できます。また、適度な硬さも保たれ、扱いやすい構造とされています。
- レンズ表面の含水率が高いため、角膜との摩擦を軽減し、みずみずしい快適なつけ心地をもたらすとされています。
- これは、高含水レンズと低含水レンズそれぞれのメリットを両立させた「いいとこどり」の構造であるといえるでしょう。
夜までうるおいたっぷり
このレンズは、長時間の装用においても目の乾燥を軽減し、うるおいを保てるように工夫されています。
- <涙液成分の配合>
レンズには、涙液に含まれる成分である「フォスファチジルコリン」が配合されています。この成分が涙と調和することで、自然なうるおいをサポートするとされています。 - <独自の「スマーティアーズテクノロジー」>
この技術は、涙の蒸発を防ぐサポートを目的として開発されました。 - <低含水コア設計の相乗効果>
前述の通り、レンズコア部分の含水率が低いため、レンズ全体での水分蒸発量は、含水率が高い一般の商品と比較して少なめであると考えられます。
これらの技術と構造により、うるおいたっぷりのつけ心地が夜まで持続することが期待できます。
トップクラスの酸素透過率
コンタクトレンズを選ぶ上で、目の健康を維持するための「酸素透過率」は重要な指標の一つです。
- <酸素透過率とは>
レンズがどれだけ多くの酸素を目に届けるかを示す数値で、数値が高いほど酸素を良く通します。 - <角膜と酸素>
角膜には血管が通っていないため、空気中のわずかな酸素を涙を介して取り込んでいます。レンズを装用すると、この酸素供給が妨げられ、酸素不足(低酸素症)になると、目のトラブルを引き起こす可能性があります。 - <トータルワンの優位性>
デイリーズトータルワンの酸素透過率は、トップクラスに高い水準(Dk値:156)にあります。
これにより、角膜に必要な酸素が十分に届けられ、角膜の酸素不足によるトラブルを防ぎ、目の健康をサポートする効果が期待できます。
デイリーズトータルワンのラインナップ&スペック表
ラインナップとしては、近視用の「デイリーズトータルワン」と、遠近両用の「デイリーズトータルワン マルチフォーカル」の2種類が発売されているようです。
機能性は変わらないそうなので、ご自身の目の状態に合った商品をお使いください。
デイリーズ トータル1
デイリーズ トータル1は、近視用のコンタクトレンズです。ベースカーブが2種類あるので、自分に合ったレンズを選びやすいでしょう。
具体的なスペックについては、以下の表をご参照ください。
| 商品名 | デイリーズ トータル1 |
|---|---|
| 枚数 | 30枚 |
| 内容量 | 片眼1ヶ月分 |
| タイプ | 近視用 |
| ベースカーブ | 8.5/8.8 |
| 直径 | 14.1 |
| 含水率 | 33%(レンズコア部分) |
| Dk値(酸素透過係数) | 156 |
| 素材グループ | Ⅰ |
デイリーズ トータル1 マルチフォーカル
デイリーズ トータル1 マルチフォーカルは、遠近両用のコンタクトレンズです。
こちらの商品は、アルコン独自の「マルチフォーカルデザイン」が採用されているとのこと。手元から遠くまで、さらに中間を見るための度数を1枚のレンズに配置することにより、見たいものを自然に見られるようになるそうです。
遠近両用のコンタクトレンズは、遠くの見え方・近くの見え方どちらもサポートしてくれるもので、老眼の症状にお悩みの方々にぴったりな商品だそうです。
デイリーズ トータル1 マルチフォーカルの具体的なスペックは、以下の通りです。
| 商品名 | デイリーズ トータル1 マルチフォーカル |
|---|---|
| 枚数 | 30枚 |
| 内容量 | 片眼1ヶ月分 |
| タイプ | 遠近両用 |
| ベースカーブ | 8.5 |
| 直径 | 14.1 |
| 含水率 | 33%(レンズコア部分) |
| Dk値(酸素透過係数) | 156 |
| 素材グループ | Ⅰ |
デイリーズトータルワンの口コミは?

ここでは、実際に「デイリーズトータルワン」を使用した方々の評判を紹介します。シルチカに寄せられた口コミから、近視用と遠近両用(マルチフォーカル)それぞれの評価をまとめ、製品の特徴がどのように体験に結びついているかを解説します。
デイリーズトータルワンの口コミ
近視用の「デイリーズトータルワン」に関する口コミでは、主に装用感の良さと長時間装用時のうるおいが高く評価されています。
- ・人にオススメされて使いました。使い心地は文句なしです。コンタクトは違和感が気になるからあまりしたくなかったんですけど、これなら違和感がないので、快適にスポーツを楽しめます。(10代/★5)
- ・レンズが薄く、つけている時も違和感が全くないので、びっくりしました。私はコンタクトを長時間つけがちなのですが、それでもつけ心地も潤いも保つことができて助かっています。(20代/★4)
- ・つけている間はすっごい快適だけど、ちょっと取りにくいのが難点…(30代/★4)
- 引用:シルチカ
デイリーズトータルワンの口コミまとめと考察
口コミからは、「生感覚」というキャッチフレーズの通り、違和感の少なさや「何もつけていないかのような装用感」が特に目立つ評価点となっています。コンタクトレンズ特有のゴロゴロ感に悩んでいる方にとっては、試してみる価値のある商品であると推測されます。
また、うるおいに関しても高評価を得ており、「水のグラデーション構造」による水分キープの仕組みが、一日の終わりまで乾燥を気にせず装用しやすい状況をサポートしていると考えられます。
一方で、「レンズが取りにくい」という意見も見受けられました。これは、目にしっかりとフィットしてうるおいを保つ設計上、外す際に難しさを感じるユーザーもいることを示唆しています。
- <アルコン社が推奨する着脱方法>
アルコン社は、鏡を見る際に下目遣いではなく上目遣いにすること、親指と人差し指をV字にして白目の部分まで優しく下げてから外すことを推奨しています。 - <着脱が難しい場合の対処法>
どうしても外せない場合は、コンタクトレンズ専門店や通販で販売されている専用の着脱器具を利用することもおすすめされます。
デイリーズトータルワン マルチフォーカルの口コミ
遠近両用の「デイリーズトータルワン マルチフォーカル」に関する口コミでは、遠近両用レンズ特有の慣れにくさの軽減や、快適なつけ心地が評価されています。
- ・息子に遠近両用コンタクトレンズを勧められて購入しました。メガネよりも快適です。(40代/★5)
- ・最初は慣れづらいと聞いていましたが、はじめからほとんど違和感なく使えました。(40代/★5)
- ・老眼鏡をかけているのが嫌で、コンタクトに変更。つけ心地がいいよと友人に言われてこちらに決めました。使ってみるととても快適で、遠くが少しぼやけますが、問題なく使えています。これからも使っていこうと思います。(50代/★4)
- 引用:シルチカ
デイリーズトータルワン マルチフォーカルの口コミまとめと考察
遠近両用コンタクトレンズは複数の度数が入っている構造上、慣れが必要とされる場合がありますが、マルチフォーカルは「はじめから違和感なく使えた」といった声が多く、慣れやすさが評価されているようです。老眼鏡の着脱が煩わしいと感じる方や、より自然な見え方を求める方に適していると考えられます。
近視用と同様に、つけ心地の良さも高く評価されています。「水のグラデーション構造」や「スマーティアーズテクノロジー」によってうるおいがサポートされるため、老眼だけでなく目の乾燥にも悩んでいる方にとって、おすすめできる商品であるといえるでしょう。
デイリーズトータルワンはこんな人におすすめ!

「デイリーズトータルワン」は、特に以下の3つの要素に課題を感じているコンタクトレンズユーザーにおすすめできる商品です。製品の特徴である「水のグラデーション構造」「独自のうるおい技術」「高い酸素透過率」から、どのようなメリットが享受できるかを解説します。
何もつけていないかのような装用感を試したい人
コンタクトレンズ特有の違和感やゴロゴロ感に悩んでいる方にとって、「デイリーズトータルワン」はおすすめの選択肢です。
快適なつけ心地の理由
トータルワンのレンズ最表面は、含水率が100%に近いハイドロジェルの層で構成されているとされています。これにより、まばたきをした際の目の摩擦が抑えられ、ストレスのない快適なつけ心地が期待できます。
何もつけていないかのような「生感覚レンズ」という体験を試したい方に、最適な商品であるといえるでしょう。
長時間の装用で目の乾きを感じやすい方にも、「デイリーズトータルワン」はおすすめです。
うるおいが持続する仕組み
涙の蒸発を防ぐサポートをする独自のテクノロジー(スマーティアーズテクノロジー)と、レンズコア部分の含水率を低くする「水のグラデーション構造」が、うるおいをサポートします。これにより、水分が蒸発しにくく、うるおいが夜まで続くことが期待できます。
スマートフォンやパソコンを日常的に長時間使用する方、あるいは目薬が手放せないといった目の乾燥にお悩みの方は、一度試してみることをおすすめします。
角膜の酸素不足を防ぎ目の健康をサポートしたい人
目の健康を重視し、角膜の酸素不足を防ぎたいと考えている人にとって、「デイリーズトータルワン」は推奨される商品です。
- <トップクラスの酸素透過率>
デイリーズトータルワンは、Dk値(酸素透過係数)156という、トップクラスに高い酸素透過率を達成しています。 - <酸素供給の重要性>
角膜(黒目)は血管がないため、外部から酸素を取り込む必要があります。酸素不足が続くと、黒目の部分に血管が侵入したり、角膜細胞が減少したりするなど、目の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。 - <目の負担軽減>
特にコンタクトレンズの使用頻度が高い方は、トータルワンのような酸素透過性に優れている商品を選ぶことで、角膜への負担を軽減できる可能性が高まります。目の健康をサポートするためにも、酸素透過率の高いコンタクトレンズの使用が推奨されます。
デイリーズトータルワンを使うときの注意点

「デイリーズトータルワン」を安全かつ快適に使用し、目の健康を維持するためには、いくつかの重要な注意点を守ることが推奨されます。コンタクトレンズ初心者の方だけでなく、初めて本製品を試す方も、以下の項目を確認してください。
眼科の検査・処方を受けよう
コンタクトレンズを使用する際は、まず眼科を受診することが必須とされています。
- <目の状態の確認>
問診や視力検査を通して、レンズがご自身の目に合っているか、レンズデータ(度数やベースカーブなど)が適切かを眼科医に判断してもらう必要があります。 - <事前の確認を推奨>
受診の際には、「デイリーズトータルワン」の使用を希望する旨を伝えてください。ただし、眼科によってはコンタクトレンズの処方を行っていない場合があるため、事前にホームページや電話で確認することが推奨されます。
コンタクトレンズの処方箋(装用指示書)のもらい方は下記コラムで解説しています。
コンタクト処方箋のもらい方・使い方【眼科選び/期限/料金/再発行も解説】装用時間・使用期間を正しく守ろう
レンズを装用する時間と期間は、目の負担を避けるために必ず守る必要があります。
- <装用時間の遵守>
コンタクトレンズには、一般的に装用時間が定められています。これを守らずに使い続けると、目に大きな負担がかかる可能性があります。 - <慣れるまでの段階的な装用>
装用時間は、初日から徐々に伸ばしていくのが一般的です。最終的に終日装用が可能になる場合でも、慣れやすさや目の状態には個人差があるため、具体的なスケジュールは必ず眼科医にご相談ください。 - <ワンデーの使用期間厳守>
「デイリーズトータルワン」は一日使い捨てのワンデータイプです。一度外したレンズを再装用したり、2日以上にわたって使用したりすることは厳禁です。汚れや菌の付着により、眼病を引き起こす可能性があります。レンズを外したら、必ずそのまま破棄し、新しいレンズを使用してください。
コンタクトレンズの使用期間と使用期限の違いについては下記コラムで解説しています。
【注意】コンタクトレンズは使用期間とは?使用期限との違いを解説目の定期検査を受けよう
コンタクトレンズを使い続ける場合、自覚症状の有無にかかわらず、目の定期検査を受けることが推奨されます。
- <異常の早期発見>
長期間使用しているうちに、視力が変化したり、自覚症状がないままに眼病を発症していたりする可能性があります。 - <特に注意が必要な人>
正しいルールを守れていない方は特に要注意です。目の状態が悪化しているケースも考えられるため、3ヶ月に1回を目安に眼科を受診し、検査を受けてください。
目の異常があれば眼科を受診しよう
装用中に痛みやかゆみ、充血などの目の異常に気づいた場合は、直ちに眼科を受診することが推奨されます。
- <早期解決の重要性>
トラブルが発生した場合でも、早めに検査や適切な治療を受けることで、症状の悪化を防ぐことができます。 - <不安解消>
軽い違和感であっても、「もしかしたら病気かもしれない」という不安を解消するためにも、眼科医に相談することがおすすめされます。
デイリーズトータルワンを買うには?

「デイリーズトータルワン」の購入は、眼科の受診から始まります。ここでは、安全に購入するためのステップと、購入場所の選択肢(実店舗と通販サイトの比較)について解説します。
まずは眼科を受診する
コンタクトレンズを初めて使用する方、トータルワンを試す方、またはしばらく定期検診を受けていない方は、まず眼科を受診することが推奨されます。
- <受診の目的>
目を検査することで、ご自身の目に合った正確なレンズデータ(度数やベースカーブなど)を知ることができます。 - <定期検査の重要性>
目の健康維持のためにも、一度の受診で終わらせず、3ヶ月に一度を目安に定期的に検査を受けることが推奨されます。
実店舗もしくは通販サイトで購入する
ご自身のレンズデータが確定した後、購入は基本的に実店舗(コンタクトレンズ専門店など)または通販サイトのいずれかから行えます。
| 購入方法 | 特徴・メリット | 注意点・デメリット |
|---|---|---|
| 実店舗 | 眼科の処方箋を提出して購入するのが一般的です。・不安や疑問点があれば、店員に直接相談できる点が魅力です。 | 通販サイトと比較して商品の価格が高めになる可能性があります。 |
| 通販サイト | 商品の価格が実店舗よりも低めに設定されている傾向があります。・スキマ時間で手軽に購入できる点が魅力的です。 | 処方箋の提出を推奨される場合や、自分でレンズデータを入力して購入する場合があり、自己責任が伴います。 |
通販で買う際のポイントはこちらのコラムでご紹介しているので、併せてお読みください。
「コンタクトをネットで購入したいけど不安…」ネットで買う際のポイントをご紹介安く買うなら通販サイトがおすすめ
実店舗と通販サイトにはそれぞれメリットがありますが、購入費用を抑えたい場合は、通販サイトの利用がおすすめされます。
- <価格が安い理由(客観的根拠)>
実店舗は、家賃、人件費、設備費などの運営コストが高くなりがちであり、利益を出すために商品価格にこれらのコストが上乗せされることがあります。一方、通販サイトは運営コストを比較的抑えられるため、その分商品価格を低く設定できる傾向にあります。 - <さらにお得に買う方法>
通販サイトでは、まとめ買いや定期便、クーポンといったサービスが提供されていることが多く、これらを利用することでさらにお得に購入することが期待できます。 - <購入頻度が高い方へ>
コンタクトレンズは使用頻度が高いほど費用もかさむため、コストパフォーマンスを重視したい場合は、通販サイトの利用がおすすめされます。
コンタクトレンズをどこで買うと安心して低価格で買えるのかは下記コラムで検証結果を発表しています。
コンタクトレンズはどこで買うのが安い?おすすめの購入方法を徹底比較《結果発表》デイリーズトータルワンの最安値をシルチカでチェック!

アルコンの「デイリーズトータルワン」は、独自の技術により「生感覚」の装用感を実現したワンデーコンタクトレンズです。目の乾燥や酸素不足に悩む方など、多くの方におすすめできます。
| トピック | 主要なポイント |
|---|---|
| 生感覚を支える構造 | 「水のグラデーション構造」により、レンズコアは低含水で水分の蒸発を抑え、表面は高含水で摩擦を抑え、快適なつけ心地を実現。 |
| うるおいの持続性 | 涙液成分を含む「フォスファチジルコリン」や「スマーティアーズテクノロジー」により、夜までうるおいが持続することが期待できる。 |
| 目の健康への配慮 | Dk値156というトップクラスの酸素透過率で、角膜の酸素不足を防ぎ、目の健康をサポートする効果が期待できる。 |
| 購入時の注意点 | 安全な使用のため、眼科での検査・処方、正しい装用時間・使用期間の遵守、定期検査を継続することが強く推奨される。 |
シルチカでは、デイリーズトータルワンを含め、さまざまなコンタクトレンズの最安値をチェックできます。少しでもお得に購入したい方は、ぜひご活用ください。
「シルチカ」でコンタクトレンズを探してみるよくある質問
-
「生感覚レンズ」とは何ですか?
アイケア医療機器メーカーのアルコンが発売しているコンタクトレンズ、「デイリーズトータルワン」のキャッチフレーズです。レンズ表面の含水率が100%に近く、まるで何もつけていないかのような、非常に快適な装用感が期待できることから名付けられているそうです。
-
デイリーズトータルワンは他のコンタクトレンズとどう違いますか?
従来のコンタクトレンズと異なる点は、レンズのコア(中心部)と表面で含水率が異なる「水のグラデーション構造」を採用している点です。これにより、高い水分量でつけ心地の良さを保ちつつ、水分の蒸発を抑えるサポートが期待できます。また、酸素透過率(Dk値156)がトップクラスに高い点も特徴の一つといわれています。
-
デイリーズトータルワンが「取りにくい」と感じる時の対処法はありますか?
一部の口コミでは、目にフィットする装用感の良さから「取りにくい」と感じる方もいます。アルコン社は、鏡を見る際に上目遣いにすることや、親指と人差し指をV字にして白目の部分まで優しく下げてから外す方法を推奨しています。どうしても取りにくい場合は、コンタクトレンズ専用の着脱器具を利用することもおすすめされます。

この記事を書いた人シルチカ探偵
SILCHIKAはコンタクトレンズの価格、送料、ショップ特徴など気になる情報を公平、且つ、中立的な立場でお届けしています。
毎日が素敵なお買い物になるよう"知る" をもっと "近く" に。溢れる情報から、本当の最安値をスマートに。



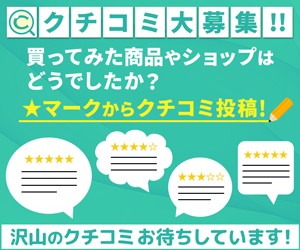



![ワンデーアキュビュー オアシス [90枚入り] (近視)](https://silchika.jp/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBMk1PQXc9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--2459d79d698269686710e06b2df56ef673dcc18e/product_154.webp)
![ワンデーアキュビューモイスト [90枚入り] (近視)](https://silchika.jp/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBMjhPQXc9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--9ceb42b8d9484c4784db9afae908525c4041186a/product_166.webp)
![ワンデー アキュビュー トゥルーアイ [90枚入り] (近視)](https://silchika.jp/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBMndPQXc9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--855428be67c52ac3cf6e09852015c359d0a01536/product_163.webp)

![ワンデーアキュビュー オアシス [30枚入り] (近視)](https://silchika.jp/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBMklPQXc9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--0b64566381b980b62d3df8b12a4fd29269c08e9d/product_153.webp)
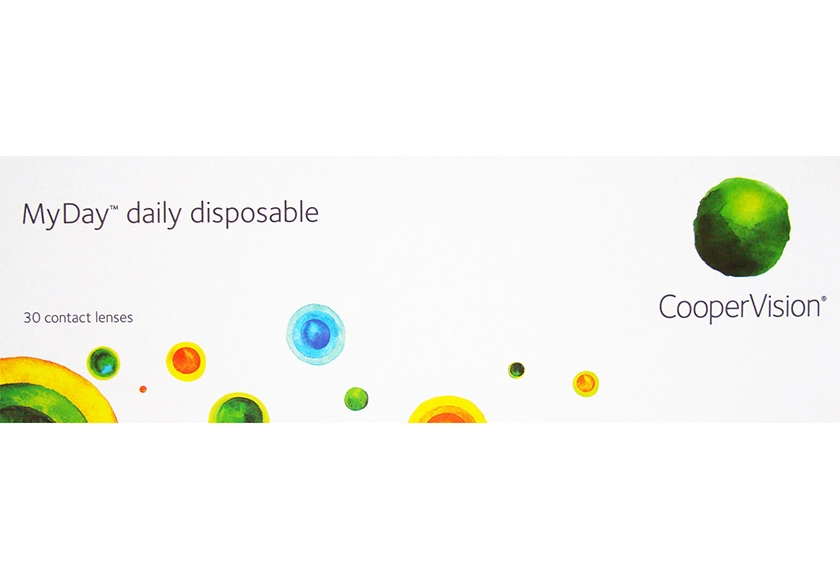
](https://silchika.jp/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBem9QQXc9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--4445544ab11c2285c48e9d4dddb353e51bc0f99a/product_501.webp)


![ワンデーピュアうるおいプラス[32枚入り] (近視)](https://silchika.jp/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBM0lPQXc9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--0a7a73dd3ddb78373beab2dd474068458c4e8c41/product_169.webp)
![ワンデーアキュビューモイスト [30枚入り] (近視)](https://silchika.jp/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBMjRPQXc9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--69527572f16b9f0fe1df1e1ff80d83ef2bdf3db2/product_165.webp)
![ワンデー アキュビュー トゥルーアイ [30枚入り] (近視)](https://silchika.jp/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBMjBPQXc9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--546e8d22fa4ab964db846ef89f9855c5e1a49b27/product_164.webp)